
■はじめに
冷却CCDカメラの実力が認識されるようになって久しいですが、銀塩写真と違ってアマチュアにとっての歴史が浅いことから、一部の人を除いて十分に使いこなしていないのが現状です。
札天では生田会員がすでに以前からSBIG社のST-6を用いて、札幌市内からでも見事な銀河の写真をものにしておられます。不肖、私も昨年初めにSBIG社のST-8を購入しましたが、頻繁に使い始めたのは今年の冬を挟んだ昨年の秋とこの春の数ヶ月にすぎません。
天文雑誌に掲載される見事なCCD画像にはため息が出るばかりで、いつかはこんな画像をと・・・、と思って腕を磨いている次第です。
■CANとは?
最近天文雑誌などで話題になっている"CAN"とは、CCD Astronomy Networkの略称です。これはインターネットサーバーを利用したメーリングリストで、アマチュアCCD写真家の意見交換の場として1996年に設立されました。加入者は全国で300人以上と言われていますが、詳しいことはわかりません。道内では私の他に生田氏、円館氏、藤井氏など10名程度が名を連ねているはずです。
参加希望の方は、can@nhao.go.jp 宛に題名には参加希望と書いて、本文には本名を書いてメールして下さい(挨拶などは不要です)。数日以内に案内メールと共にメールの配信が始まります。1日あたりほぼ2-3通のメールが届きますが、全く来ない日が数日続くこともありましたが、大丈夫でした。なお参加費は無料ですので、皆さんもお試し下さい。
■CCDカンファレンス開かる
CANの仲間のオフラインミーティングが昨年から始まりました。これをCAN Party、CANPと呼んでいます。昨年は京都のダイニックアストロパークで開かれましたが、今年は東京は渋谷区初台のASCII本社会議室で開かれました。何故、ASCII本社かといえば、ステラナビゲーターやスカイウォッチャー誌を発行しているアストロアーツの後援を受けているからです。アストロアーツはASCIIグループの一員であるためです。
■日 程
日程は次のようでした(あくまで予定ですが)。
1998年5月16日(土)
13:00-13:10)挨拶など
13:10-17:45)特別、一般講演
・デジタル現像と色彩理論の基礎(蒔田 剛)
・天体画像に潜む情報への期待(冨田弘一郎)
・各社CCDカメラのユーザーによるレビュー
・LRGB4元カラー合成プロセス実演(岡野邦彦)
18:00-20:00)懇親会
20:00-22:00)シンポジウム・冷却CCDカメラの現状と問題点
1998年5月17日(日)
09:00-11:30)一般講演
・超新星のCCD捜索と観測のレビュー(清田清一郎)
・惑星のCCD観測レビュー(阿久津富夫)
・冷却CCDが切り拓くデータベース天文学の未来〜MISAOプロジェクト〜(吉田誠一)
11:30-12:00)総括討議など
■会場まで
日曜の夕方から長野県の仕事先に行くようになったので、公私の日程はぴったりと合いました。それでも会場に着いたのは、14時頃になってしまいました(普段乗り慣れない京王線に乗って見事に路線を間違ってしまったのでした)。
京王新線初台駅から東へ向かって巨大な東京都庁などを仰ぎ見ながら行きますと、ASCIIの本社にたどり着きます(写真-1)。守衛に参加証を見せて地下2階へ。すでに受付には誰もおらず、蒔田氏の公演中でした。

氏はキャノンに勤めるエンジニアで、デジタル色彩の話を熱心に講演されていました。要点は、実際の色彩とPCが出せる色彩、さらにモニターが出せる色彩を比べてみると、モニターでは限られた色彩しか表現できないことがわかります。その他、いろいろといわれていましたが、よく理解ができないままに終わってしまいました。それに持ち時間をだいぶんオーバーしましたが、これはちょっといただけませんね。
■講演から
・冨田弘一郎先生
天文ガイドなどでおなじみの冨田先生は自分史を語りつつ、古い天体写真のお話や新天体発見の様子などをわかりやすくお話しされました。中でもご幼少のみぎりの写真を本邦初公開でしょうか?いつものように特徴のあるしゃがれ声で話されました。
天体写真からは数多くの新天体(彗星、新星、超新星、変光星など)が発見されていますので、アマチュアの撮像したCCD画像からもその情報を生かすことが期待されています。なお、例として私の撮影したHB彗星のスペクトル写真もありましたが、ちょっと赤面気味でした。

・岡野邦彦氏
天文雑誌でおなじみのCCDの神様、岡野邦彦氏の登場です。岡野氏は雑誌写真と同じにスポーツ刈りで赤ら顔の方でしたが、声はすっかり期待を裏切られました。もっと野太いい声を予想していたのですが、わりあいと高い声で優しくしゃべる方でした。
今回はLRGB4元カラー合成の実演で、パソコンを使っての画像処理を見せてくれました。LRGBについて簡単に説明しますと・・・、カラー画像は輝度信号がシャープであれば色信号はぼけていても良いという原理を使用しています。これはすでにカラーTV放送で用いられています。天文用CCDでは大幅な撮像時間の短縮につながるメリットがあります。
実際の手順は、煩雑ですが次のとおりです。
まず、なるべく鮮明なモノクロ画像を撮像します。次に同じ構図でRGB三色画像を撮像します(このときビニングしておくと撮像時間を短縮できます)。RGB画像をLab画像に変換し、Lチャンネルは捨てます(abチャンネルはカラーです)。そしてモノクロ画像をLチャンネルとみなして、Lab画像を統合してカラーにします。このとき、ab画像はすこしぼかしておきます。
とまあ、かなり面倒くさい手順ですが、その合成後の仕上がりは目を見張るばかりです。

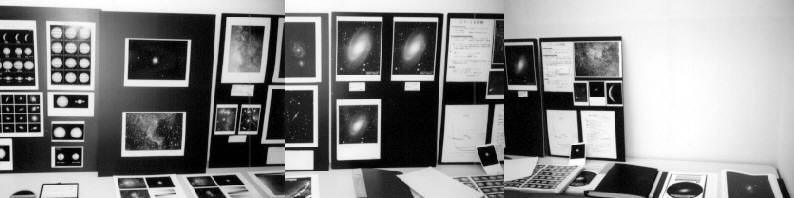
left: famous Dr. Kunihiko OKANO, played as CCD instructor on this meeting
■懇親会にて
懇親会の幹事は岡野氏で、酒(生ビールのみ)とつまみの量にはかなり自信のある旨、発言されました。乾杯の発声は冨田先生でした。私はHB彗星のスペクトルの件でお世話になった冨田先生にご挨拶をして、スペクトル観測やらその他の雑談をさせていただきました。この内しし群の観測については、南半球で観測すると後ろから見ることになるので面白いだろうとか、先生自身は内之浦で観測される予定であることなどを伺いました。
スペクトル観測の件では、次のお話がありました。
(1)私が写したHB彗星の件
カラーフィルムでも分光観測には問題ない。しかし残念なことには、フィルムは同じ銘柄で統一しておくべきだったこと。解析のために、構成の分光スペクトルを撮影するように指導される。
(2)HB彗星のNaテイル
イタリアのチームが撮影したNaテイルに関しては、Na用のナローバンドフィルターを使用していたが、これは国立天文台でも一応用意だけはしていたのこと。また、イタリアチームだけがNaテイル検出したのは、本来コマの部分を狙っていたが広角のレンズを使用したために尾も写っていたことは偶然であること。また、Na用の干渉フィルターをそのうち貸与していただけるとのこと。
(3)グレーティング
分光プリズムでは赤い方が詰まってしまうので、グレーティングの方が均等に分散される。島津製作所からBosch
& Lomb製のグレーティング(レプリカ)が発売されているが、翌日これを貸与していただいたこと(期間は99年間とのことであった)。しし群の流星や明るい彗星が出現したら撮影してほしいとのことであった。
その後、自己紹介がありましたが、わりあいと初心者ないしは使いこなしていない人が多く、雑誌で見るような著名な方は数名程度でしょうか。私はロシア製のマクストフカセを使用していることを言ったため、阿久津さんほか数名の方に使用感を聞かれました。
■シンポジウムにて
シンポジウムとは言いながらも、「冷却CCDカメラの現状と問題点」というテーマで各自が使用しているカメラの感想、悪口雑言?などを発言するコーナーです。その前に、余興として私に天体のスペクトル撮影について話すよう頼まれましたので、厚顔ながら分光プリズムを用いた撮影方法について5分ほどお話ししました。もちろん、冨田先生のフォローもありましたが・・・。
さて、問題点についてはいろいろな意見が出ましたが、やはり、画像処理に関することが多かったように思います。詳細は宴会の後ということで、記憶していませんので・・・。
また、アスロトロアーツの上山氏からは、新しい画像処理ソフトであるStella
Image 2の紹介。これまでPhotoshopやPhotopublisherなどの数種類のフォトレタッチソフトを1本にしたもの。デジタル現像、LRGB合成、その他の画像処理がとても簡単にできるソフトで、お値段も25,000円とお買い得。これは良さそうです。

■2日目の講演から
2日目は朝からかなりの雨降りでした。昨日よりも10人ほど少ない雰囲気でした。
・超新星のCCD捜索と観測のレビュー(清田清一郎)
頭を短く刈った、舌足らずなしゃべりをする人でした。
最近の捜索家事情などの紹介です。佐野康男さんを含め、ほとんどの人がCCDを使っている。超新星の同定の際に小惑星や変光星などと区別するには、既存の星図では役に立たず、役に立つのは自分で撮像したフレームだけとのこと。このフレームを集めるのが楽しいのかも知れないとの評価もあり。
・惑星のCCD観測レビュー(阿久津富夫)
天文ガイドで惑星ガイドの執筆者で、見事な惑星画像でおなじみの人。栃木弁の混じる朴訥な人という感じ。
LRGBによる惑星(特に火星、木星、土星)の撮像の話題が中心でした。興味深かったのは、赤外域に強いCCDの特性を生かした赤外線観測です。富士アセテートフィルターIR
88を使えば、昼間でも木星を撮像できたとのこと。SL9彗星の時にこのことに気がつかなかったことが悔やまれたとのこと。
・冷却CCDが切り拓くデータベース天文学の未来〜MISAOプロジェクト〜(吉田誠一)
FSPACEの彗星会議室に彗星の広場を発表している、新進の大学院生の人。少し小柄。
このプロジェクトはすでに雑誌にも紹介されているが、撮像済みの画像から未知の天体を検索するシステム。ソフトは講演者が書いたもので、すでにUNIXでは動き出している。例としてあげられた天域では、未知の天体がコンマ数秒の精度で位置が求まるようになっている優れモノ。実際の運用はあと少しかかるらしい。
なお、講演の合間の休憩時間には、岡野氏によるST-7モバイルシステムのデモがありました。これは初心者あるいは非SBIGユーザーを対象としたものでしたが、20人ほどが熱心に聞いていました。

■まとめ
実は昨年の会議に行こうと思っていたのでしたが、仕事の都合により行けなかったので、今回の会合には期待していました。参加者も50数名と昨年の倍程度の人が集まりました。東京ということでCCD人口も多い上に、集まりやすいということだったのでしょう。でも、私を含めて意外に使いこなしていない人が多い、という事実を確認したような気がします。
暗い天体も短時間で簡単に撮れるが、美しい画像にするには撮影・画像処理技術が不可欠です。雑誌だけでは情報不足に陥りがちですので、やはり実際に良い作品を作っている人に会って体験談を聞くのが一番です。
来年の開催地は未定ですが、そのうちに北海道にまわってくるかも知れません。それまでにCCDについて十分腕を磨いておかねばとの思いを強くしました。
*札幌天文同好会会報「PLEIADES」へ投稿した記事です